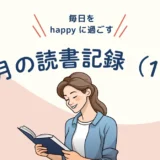よく聞かれる「不登校だった人ってどんな特徴?」
検索される言葉への違和感
インターネットで見た、不登校だった人の10個の特徴みたいなサイト。
私はそれを見て、あ~確かに~私、あてはまるなと楽しんだ半面、
ちょっと待ってよ、私の周りの不登校って、私と似たような人いたっけ?と考えました。
複数個特徴を上げれば、そりゃどれかには当てはまるでしょう。
「不登校の特徴?どういうことだ。」と考えてしまいました。
不登校経験者が実感した“多様性”
私は自分が不登校だったので、不登校友達もたくさんいました。
不登校の人たちが集まる場所に行ってみて感じたことは学校と一緒なんだなってことでした。
学校にいろんな人がいるように、不登校という同じ状況でもいろいろな人がいると知りました。
私の不登校体験:4回にわたる不登校の理由
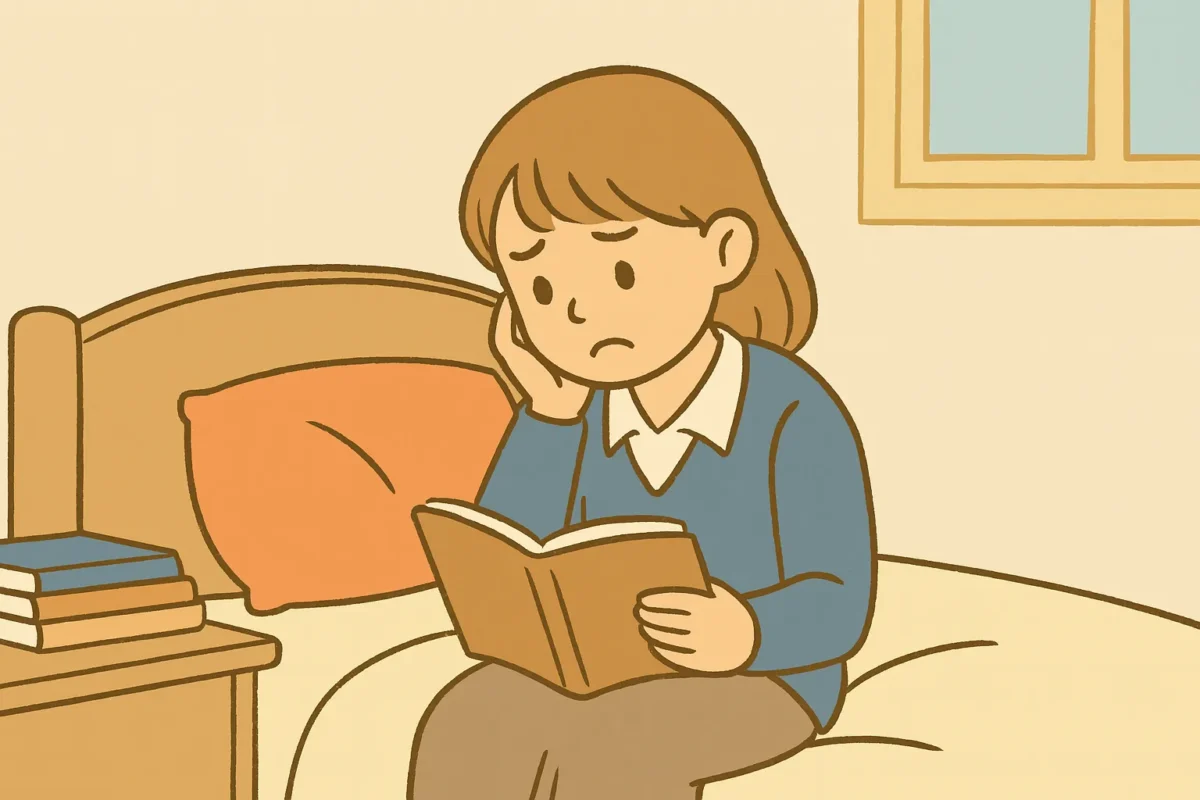
私は小学生の時に、4回不登校を経験しました。
不登校の理由はその時によって様々。元気で前向きな不登校の時もあれば、パワーを失って何もできないときもありました。学校に行けなかった時の私の状況もその時によって違いました。
ざっくりまとめると、以下の3点が大きかったように感じます。
①先生との関係
これは初めての不登校の時のこと。きっちりしたいタイプの私は、おおらかな先生ののことが理解できずにいました。
約束した日にテストが返ってこない、提出したプリントを紛失する、片づけられない先生の机(その中で、私たちのプリントがくしゃくしゃになっている)
学校の先生のことを全面的に信頼していた私だからこそ、そんな先生の姿に混乱したのだと思います。
②刺激が強すぎて、疲労からくる不調
私にとって学校とは、刺激的な場所でした。
たくさんの人がいること、絶え間なく音がすること、いろんな気持ちが混ざっていること(起こっている人もいれば、笑っている人もいる)、給食の匂いなどなど。
当時の私はそれがストレスになっていることは気づいていませんでしたが、
今思えば小さなことが積み重なってストレスになっていました。
③母子分離の不安
これは低学年の頃のこと。とにかく、家から出るのが不安だったことを覚えています。
言葉にならない、あの気持ち。旅行の時のホームシックの感じに似ている?
これはもう、どうしようもなったですね。
その他の要因も複雑に絡み合っていた
と、こんな感じで大まかに3つに分けてみました。
このほかにも探そうと思えばいくらでも学校に行きたくない、行けない理由はあったと思います。
理由は一つではなく、様々なことが混ざり合っていたと思います。
私一人でもこうなので、不登校という枠で考えたとしたら、不登校の理由というのは様々ということが想像できると思います。
「不登校の特徴」と一括りにはできない

不登校は、今の“状態”
不登校というのは、現状が学校に行けていないということですよね。
その人が学校生活の中でどんな生活をしていたかは分からないし、不登校歴が1年未満で終わる人もいれば、何年も不登校の状態を続ける人もいます。
背景も、理由も、感じ方も、すべてが個別
そうすると、不登校という今の状態が一緒なだけで、その一人一人は全く違う人です。
不登校のきっかけも理由、不登校の自分の状況をどのように受け止めているかもそれぞれです。
私は適応教室に通っていた時期があり、不登校の人と関わることが多くありました。同じ学校の中にも不登校仲間はいて、一緒に保健室登校をしていたこともあります。
不登校という状況は共通していますが、みんな全然違う人であることを、私は不登校の当事者として感じました。
「不登校だからこう」と決めつけることの危うさ
そんな中で、「不登校=〇〇」と、話すことって難しいのかなと思っています。
いろいろな本を読んだり、ネットの中の情報を見ると、私自身「私のことだ!」と、思えることもたくさんあります。
でもそれって、大学で聞いたあのバーナム効果なのでは?と思うことも…
私自身、何度も違う理由で不登校になった
繰り返しになりますが、私は何度も不登校になり、そこから抜け出せたことも、抜け出せなかった時もあります。
不登校という枠だけで、その子どもの見立てをすることって難しいですね。
私は一人だけど、不登校の時の様子が様々でした。
そして、私が不登校という枠組みで考えられることに抵抗があるのか、決定的な出来事がありました。
「不登校だから、高校行かないでしょ?」

仲が良かった友達からの言葉
小学生高学年になると、友達同士で進路の話になりますよね。
高校や大学のことまで、どんな学校がいいか、どんなキャンパスライフを送りたいのか、などを話すことがブームだった時期がありました。夢を膨らませて反すのが楽しかったんですよね。
そんな中、友達から「あぱちは学校行けないから、全日制の高校には行かないよね?」と言われたんです。
この友達は、不登校の私に理解がある友達でした。
私が感じた“ラベル貼り”への違和感
私はその時は学校に行けていた時期でした。
それもあって、私も「高校では〇〇がしたい」「将来〇〇の勉強がしたい」などと語っていました。
そんな中、友達から、「あぱちは不登校だから~」と言われたので、衝撃を受けました。
その友達は、無意識で言った言葉だと思いますし、その発言自体は自然なものとは思います。
ただ、私は強い違和感を感じました。「不登校だと、将来の道は限られているのか?」
本人の希望や特性に合った選択肢はたくさんある
そして大人になり、困り感がある子どもを支援する仕事をするようになりました。
たくさんの生徒を見ているうちに、あの時の私の違和感は当たり前だったと考えるようになりました。
現状は同じでも、同じ人はいません。同じ場面に遭遇しても人によって感じ方が違うように、不登校でもいろんなタイプの子どもたちがいました。
私はそんなひとりひとりを大切にしたいです。
「不登校」という言葉で未来を狭めないでほしい
もちろん、不登校の生徒の傾向はあると思いますし、たくさん研究されているのだと思います。
ただ不登校当事者としては、「不登校だったひとの特徴」「不登校になりやすい家庭」というワードを見ると、すこし気になる自分もいます。
まとめ:あなた(あなたのお子さん)は、たった一人だけの大切な存在

「不登校だった人の特徴」という言葉は、とてもシンプルそうに見えてとても複雑なのでは!?
私自身の体験からも、不登校の理由や背景は一人ひとり違い、同じ人でも時期によって全く異なる姿をしていました。
不登校は“その人の特徴”ではなく、あくまで“今の状態”です。
そこに至る理由や感じ方は多様であり、「不登校だからこうだ」と一括りにすることはできないと思います。(※もちろん傾向はあると思いますし、えらい人たちが考えたことですから、不登校というくくりとしては正しいのだとは思います)
大切なのは、ラベルを貼ることではなく、その子自身の考えや特性に目を向けること。
そして「不登校だから未来が限られる」のではなく、本人の希望や強みを生かせる選択肢はたくさんあるということです。
今苦しいあなたにも、明るい未来がやってきますように♪

不登校だった私も、今は大人になりました~!
あの頃は、暗いくらい世界にいたけど、今は明るくなりました!
↓「にほんブログ村」ぽちっと押して応援お願いします!