先生が私の部屋に入ってきた瞬間、心がぎゅっと縮こまりました。
善意なのはわかっていたけれど、安心できる場所に踏み込まれるのは、苦しかった。
不登校だった私にとって、家は唯一の安全基地でした。
安心を守るための関わり方

子どもの支援には、距離感を見極める力が欠かせません。
安心できる場所に踏み込みすぎると、心を閉ざしてしまうことがあります。
信頼関係が築けているかを意識し、気持ちを尊重する姿勢が大切です
先生が家に来る
私がまったく学校に行けていなかった時期のことです。
担任の先生が、家まで来てくれました。 事前に連絡はもらっていました。
私は、先生が何をしに来るのか想像できず、不安な気持ちでいました。
「何をしにきたの?!」

先生は私の部屋に入り、話しかけてくれました。
折り紙をしようと提案してくれて、私は一緒に折ることにしました。
「せっかく来てくれたから」と、子どもなりに気を使っていたのだと思います。
でも、心は完全に閉ざしてしまっていました。
踏み込まれると苦しい
先生の善意には感謝しています。
それでも、自分の安全基地に“敵”が入ってきたような恐怖を感じました。
私にとって、自分の部屋は唯一安心できる場所でした。
そこに誰かが入ることは、強いストレスにつながりました。
先生の善意を受け取らない自分、、にもストレスを感じました。
家だけが安心できる場所だった

不登校になったばかりのころは、私はずっと家にいました。
外に出ることが怖くて、学校は強いストレスの源でした。
家にいるしか選択肢がなく、自分のスペースだけが心を休められる場所だったのです。
子どもの「安心」を守る支援とは
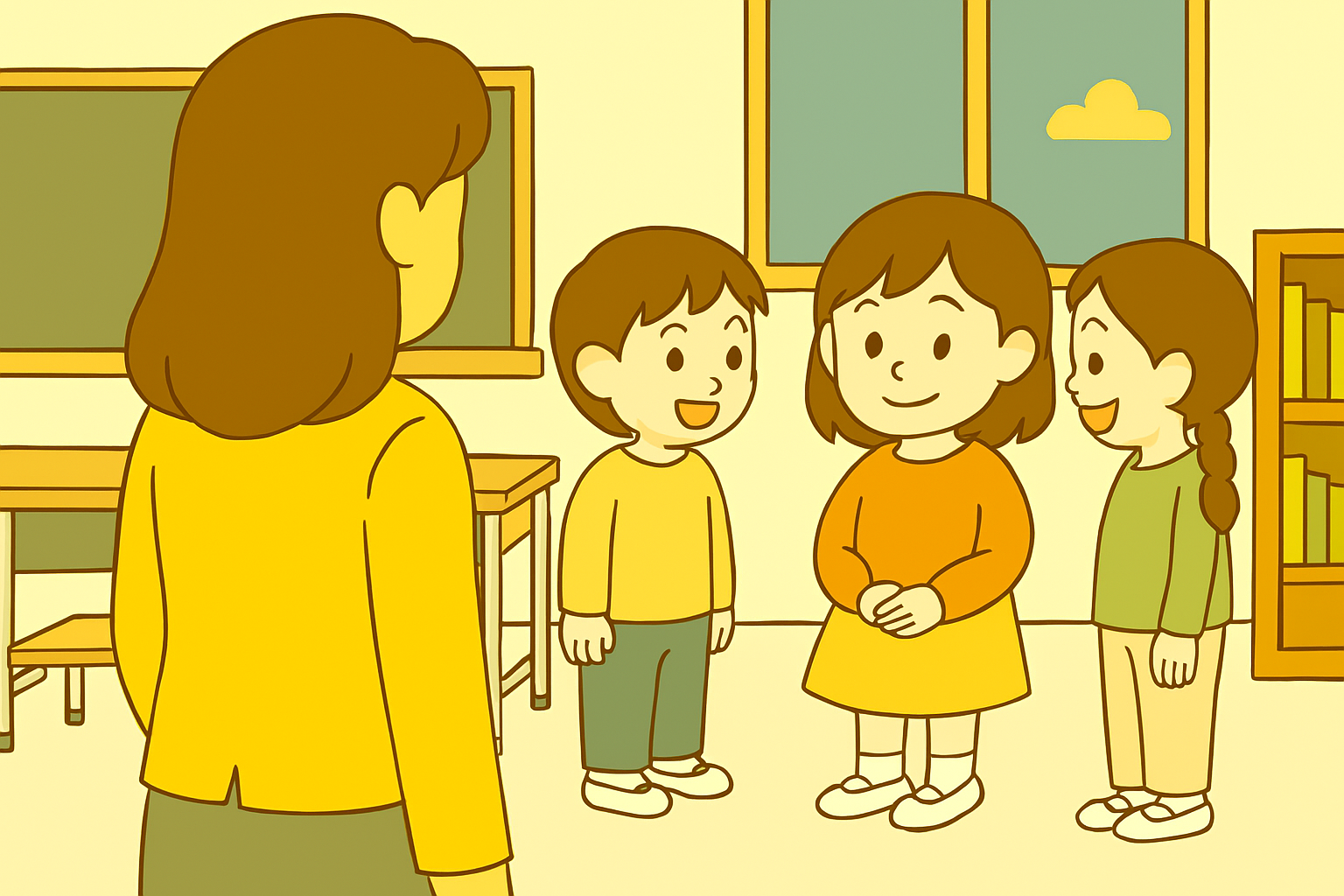
不登校の子どもに寄り添うには、
「子どもが受け止めている距離感」や「安心」を守ることが大切だと思います。
善意であっても、子どもの安心できる場所に踏み込むことは、心を閉ざすきっかけになることがあります。
私は自分の経験から、「そっとしておく」支援もあるのだと思っています。
見守るって難しいもん。

今月もまぁまぁ読めたかなっ!
せっかく、本を読める体質なんだから、難しい本にもチャレンジしたいな♪
↓「にほんブログ村」ぽちっと押して応援お願いします!



